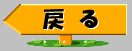森の思想
伊藤貞彦
一
生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が閉幕した。生物の問題というよりも、生物資源の保全と、そこからの儲けの持続的分けあいが論じられただけであった。そこで、生物多様性の保全のモデルケースとして、日本が里山の保全を「SATOYAMAイニシアティブ」として報告し、賞賛を得たという。
「日本列島改造論」で全国の里山を高速道路で貫き、工場・住宅団地の用地に代え、リゾート法によって残った里山をゴルフ場、遊園地、テーマパーク等に代えてきた。その結果、今や全国の里山はほとんど破壊され、その後には、売れ残った工場・住宅団地の造成地や、つぶれたゴルフ場やテーマパークの跡地が、荒涼とした草地となって横たわっているのである。この現実を前にして「SATOYAMAイニシアティブ」とは笑止千万であろう。それにしても、こんな報告を黙認した国内の共賛団体とは、いかなるものであろうか。いや、今さら言ってみても仕方ないのである。
二
原生林にせよ、市民の森にせよ、里山にせよ、鎮守の森にせよ、なぜこうした森の保全が叫ばれているのか。いわく、そこには稀少な自然がある。市民の憩いの場である。自然が豊かである。空気を浄化してくれる。水を涵養してくれる。土砂災害を防いでくれる等々といった理由が直ちにあげられるかも知れない。いずれも、人間の現在の生活に利をもたらしてくれるというわけだ。しかし、この現在の生活への利便性からこれを保全しようという論理は、生活の利便のためにこれを開発しようという論理と拮(きつ)抗(こう)する関係にあり、商品経済を基盤とした市場社会にあっては、対等のものでしかない。
ここで、意地の悪い問いを発してみよう。稀少な自然がなければ、市民に憩いを提供しなければ、要するに生活に当面の利便をもたらさなければ、森などどうなってもよいのか、と。この問いを否定できなければ、わたしたちは商品経済の論理から脱する事はできないであろう。そうなれば、わたしたちはもはや資本主義に屈伏する他ないのである。 この国でも、環境や自然保護が叫ばれて、すでに40年余が経過している。わたしたちは、この間に、どれだけ自らの環境・自然保護の思想を深め得たかが問われているののである。
三
本年夏より、「茅野(ちの)学」という試みに繰り入れられている。市図書館の企画で、郷土(長野県茅野市)の足元を問い直そうというもので、わたしの関わっているのは、この地に残るこの国の原初のクニの姿をさぐってみようというものだ。この地には、日本の古代史や日本民俗学が注目しつつもその実態が不明の、「ミシャグチ」という、原始共同体のカミの痕跡が残されている。それを明らかにする事は、大和朝廷の国家統一以前のクニと、そうしたクニを必然化した共同幻想の一端を明らかにする事につながる。まあ、問題はとてつもなく大きいが、そのための極小の一歩をというのが、この学の目的といえる。
そこで、「ミシャグチ」であるが、これはこの世の外から来て巨木に憑き、この地の生命を活性化する霊威と考えられている。この霊威=カミの降りる場を湛(たたえ)といい、巨木を中心とした小さな森を形成している。こうした森は沖縄の御嶽(うたき)や韓国の堂(タン)にもみられるもので、「万葉集」で杜と書いてモリと読ませるも、これに通じている。 森は、人間の原郷(誕生地)であるが、人間が物的生活と共に精神史たる内面史を生み出した母胎である。それは、人間に属するものではないが、人間の外部として、人間の生活の限界性を照らす鏡でもあるといえる。人間が、物的心的に生活に行き詰まった時そこにまで戻って問い直す場としてあるといってもよい。それ故、森はたかだか200年程の商品経済体制に所属するような存在でなく、商品経済の論理で開発や保護を論ずるようなものでもない。
稀少性だの利便性などに関わりなく、森はそれ自体で出来得る限り手つかずで残すべき存在である。それは、人間の生活を照らす外部であると共に、人間の歴史の母胎であるからだ。外部や母胎を喪う時、わたしたちの生活や歴史は、その生命力を喪うといってよい。
すべての村や町、あらゆる地域に手つかずの森を確保する事を、里山の保全に代って提起したいと考えている今日この頃である。
(2010年12月)
このページの頭に戻ります
前ページに戻ります
[トップページ] [全国自然保護連合とは] [加盟団体一覧] [報告・主張] [リンク] [決議・意見書] [出版物] [自然通信]